HbA1cとは?
HbA1c(ヘモグロビンA1c)は、過去1〜2か月間の血糖コントロール状態を反映する指標です。
血液中のヘモグロビン(赤血球に含まれるたんぱく質)に、ブドウ糖が結合した割合を示しています。
なぜ1〜2か月の平均なの?
赤血球の寿命は約120日ですが、血液は常に新しいものと入れ替わっているため、直近1〜2か月間の平均的な血糖値を反映すると考えられています。
一度糖が結合すると離れない性質を持つため、HbA1cの値は「血糖の履歴」を映し出すものです。
HbA1cの基準値(日本糖尿病学会2024より)
日本糖尿病学会の「糖尿病診療ガイドライン2024」では、HbA1cの目標値を次のように示しています。
- 血糖正常化を目指す場合:HbA1c 6.0%未満
- 合併症予防を目指す場合(標準的目標):HbA1c 7.0%未満
- 治療が難しい場合(高齢者や低血糖リスクあり):HbA1c 8.0%未満
👉 つまり「まずは7.0%未満を目標に、可能であれば6.0%未満へ」というのが一般的な方針です。
(参考:日本糖尿病学会「糖尿病診療ガイドライン2024」)
HbA1cを患者さんに説明するときのコツ
HbA1cという言葉は専門的すぎて、患者さんにそのまま伝えてもピンと来ないことがあります。
栄養指導の現場では、比喩やシンプルな言葉を使うと理解が深まります。
トーク例
- 「HbA1cは、ここ1〜2か月の血糖の“平均”を表す数字です」
- 「今日の努力ではすぐ変わりませんが、続けることで必ず数字に表れます」
- 「一度の食事よりも、普段の積み重ねが大切なんです」
HbA1cと血糖コントロールの関係
HbA1cの数値は、合併症リスクと密接に関係しています。
例えば、HbA1cが 7%を超える状態が続くと、糖尿病網膜症・腎症・神経障害などの合併症リスクが上昇すると多くの研究で報告されています。
そのため、患者さんには「数字を見るだけでなく、日々の生活習慣を整えることがHbA1c改善につながる」と伝えることが重要です。
まとめ
- HbA1cは「過去1〜2か月の平均血糖値」を反映する指標。
- 日本糖尿病学会ガイドライン2024では、標準目標は7.0%未満。
- 栄養指導では「HbA1c=血糖の平均点」と伝えると理解されやすい。
- 数字よりも、毎日の積み重ねがHbA1c改善のカギになる。
👉 管理栄養士として患者さんに説明するときは、難しい理屈ではなく、行動につながる言葉で伝えていきましょう。


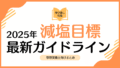
コメント