導入文
糖尿病の栄養指導の中で、「朝食は必ず食べましょう」と伝える場面は多いですよね。
でも患者さんに「なぜ朝食を食べないといけないのか?」を聞かれると、シンプルに答えるのが難しいと感じることもあると思います。
実際、朝食には
- 夜間の絶食を終えて血糖を安定させる
- 体内時計をリセットして代謝リズムを整える
- 過食や夜食を防ぐ
といった役割があり、血糖コントロールの土台になります。
ここでは、日本糖尿病学会や厚生労働省などのエビデンスをもとに、現場ですぐ使える朝食指導のポイントを整理します。
1. 朝食は血糖値の乱高下を防ぐ
朝は“体が燃料切れ”の状態です。朝食を抜くと、お昼に血糖値が急に上がりやすく、食後高血糖を招きます。さらに満腹感が続かず、夕食や夜食で食べすぎる原因にもなります。
👉 指導のコツ
- 朝食エネルギーは 1日の20〜30%を目安に(※ただし必要エネルギーは個人差があるため、かかりつけ医や管理栄養士の指示に従ってください。)
- たんぱく質(卵・納豆・ヨーグルトなど)を必ず入れる
- 主食は白米だけでなく雑穀や全粒パンも活用
「朝ごはんは車のエンジンをかけるようなもの」と例えると、患者さんにもイメージしやすいです。
2. 体内時計を整えて代謝をサポート
体内時計は、血糖やホルモンの分泌リズムに関わっています。朝食を食べることは、この時計を“リセット”する合図です。
朝食を抜くと、生活リズムが後ろにずれて夜更かし・夜食の悪循環につながりやすくなります。
逆に朝食をとると、日中の活動スイッチが入り、血糖の上がり方も安定します。
3. エビデンスから見る朝食欠食のリスク
厚労省の報告や疫学研究では、朝食を抜く人に以下の傾向が示されています:
- 肥満や高血圧のリスクが上がる
- 脳卒中の発症リスクが高まる可能性
- HbA1cや体重管理がうまくいきにくい
観察研究のため注意は必要ですが、「朝食をとる習慣がある人の方が、血糖・体重・血圧のコントロールが安定しやすい」と説明できます。
4. 糖尿病 食事指導での実践ポイント
糖尿病患者さん向けに、現場で提案しやすい朝食の組み立て例です。
- エネルギー量:400〜500 kcal程度(女性)/450〜600 kcal程度(男性)
- たんぱく質:15〜20 g(卵+納豆、ヨーグルト+チーズなど)
- 食物繊維:野菜や果物をプラス(例:野菜スープ、果物1皿)
- 順番:野菜→たんぱく質→主食の順に食べると血糖値の急上昇を防ぎやすい
👉 忙しい日の“最小セット”
- おにぎり+野菜スープ+ゆで卵
- 全粒パン+無糖ヨーグルト+サラダ
- サンドイッチ(卵や野菜入り)+牛乳
「ゼロより、まずは一口でも」と伝えることが大切です。
5. よくある患者さんの声と対応
- 「朝は食欲がない」→ 夕食を軽めにして、まずはヨーグルトや牛乳から。
- 「時間がない」→ おにぎりやサンドイッチなど“持ち出せる朝食”をすすめる。
- 「菓子パンなら食べられる」→ たんぱく質や野菜を足して“バランスを改善”。
- 「朝を抜いた方が体重が減る」→ 長期的には肥満や血糖悪化のリスクがあると説明。
まとめ
朝食は、糖尿病の血糖コントロールに欠かせない生活習慣です。
- 血糖の急上昇を防ぐ
- 体内時計を整える
- 過食や夜食を防ぐ
これらを根拠を持って伝えることで、患者さんが納得して習慣化しやすくなります。
「毎日・同じ時間・バランスよく」を合言葉に、個々の生活に合わせた朝食提案をしていきましょう。
参考文献
- 日本糖尿病学会「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン 2024」
- 厚生労働省「食生活指針の解説要領」(2016年改定)
- WHO「Healthy Diet」
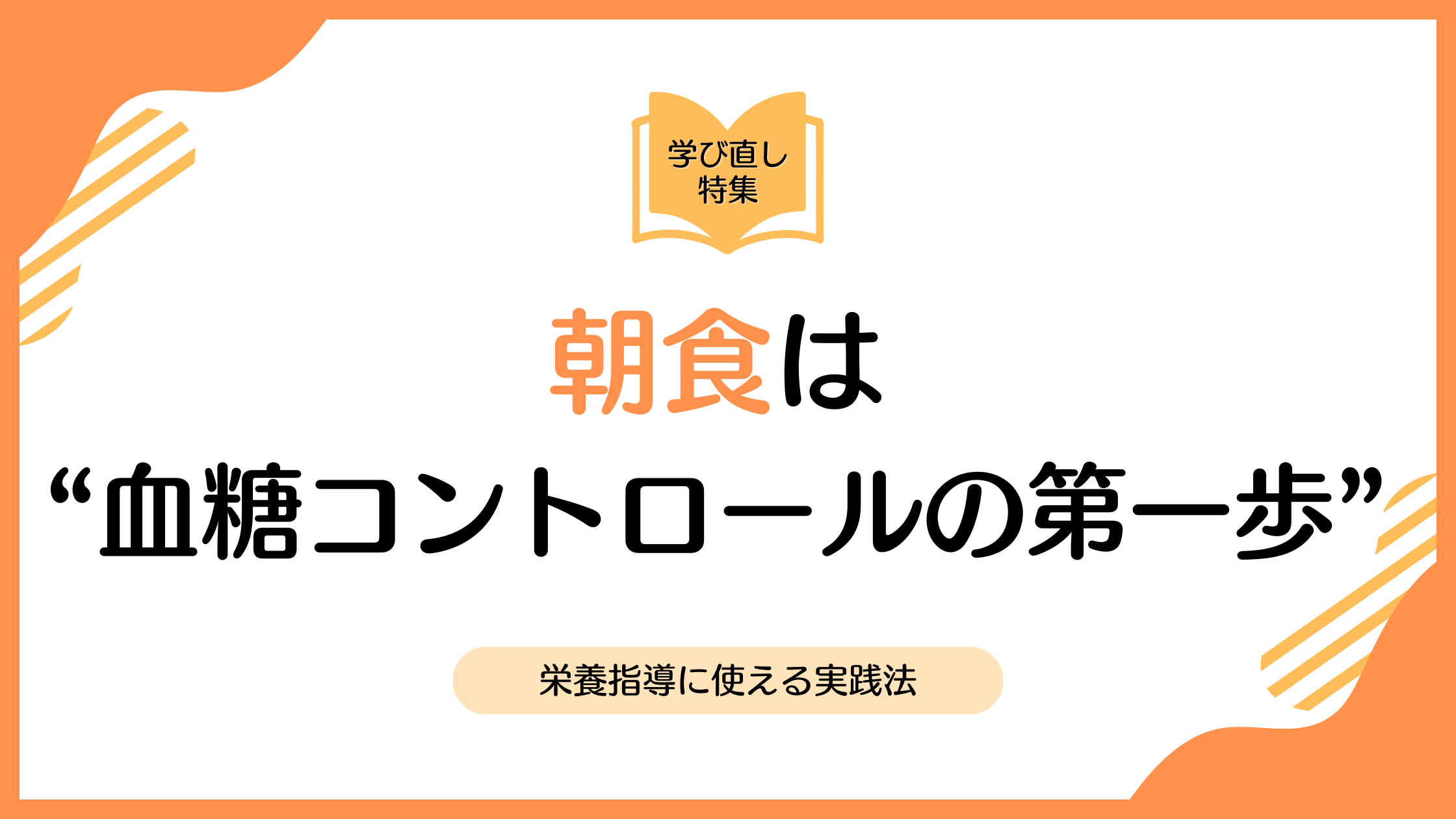


コメント