栄養指導で必ず伝えたい!
なぜ“主食の工夫”が血糖管理につながるのか?
栄養指導の現場で「主食は白ごはんが好きだから変えたくない」という声をよく聞きますよね。
でも、主食を少し工夫するだけで血糖値の上がり方は大きく変わります。
今回は、白米から麦ごはんや玄米へ工夫する意味と、患者さんへのわかりやすい伝え方を紹介します☕️
1. 主食を工夫して血糖値をゆるやかに
主食の工夫とは?
主食の工夫とは、白米をそのまま食べるのではなく、食物繊維が豊富で吸収をゆるやかにする食品へ置き換えることです。
例えば…
🍚 白米 → 麦ごはん、雑穀米、玄米へ
👉 ポイントは 「糖の吸収をゆっくりにする」 こと。
2. 食物繊維の比較データ
炊いたごはん150gあたり
| 種類 | 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 | 合計 |
| 白米ごはん (精白米) | 0.45 g | 1.8 g | 2.3 g |
| もち麦ごはん (白米30%混ぜた場合) | 0.90 g | 2.57 g | 3.5 g |
| 玄米ごはん (100%炊飯) | 0.75 g | 2.10 g | 2.9 g |
📌 補足
- もち麦は白米に30〜50%混ぜるのが一般的(表は30%で計算)
- 玄米は100%炊飯での数値
💡 指導例
「白ごはんをもち麦ごはんに変えると食物繊維は約1.5倍、玄米にすると約1.3倍に増えます。食物繊維が増えると血糖値の上がり方もゆるやかになりますよ。」
3. なぜ効くのか?
- 白米:消化吸収が早く、血糖値が急上昇しやすい
- 麦・雑穀・玄米:食物繊維が多く、糖の吸収を遅らせる
✅ 食後血糖の上昇を抑える
✅ 満腹感が持続する
✅ 腸内環境の改善にもつながる
特に大麦や雑穀に多い 水溶性食物繊維(β-グルカン) は、胃の中でジェル状になり、糖の吸収をゆっくりにします。
4. 患者さんへの伝え方のコツ
患者さんには専門用語を避けてシンプルに:
- 「麦ごはんは、糖の吸収をゆっくりにしてくれる働きがあります」
- 「麦ごはんをまとめて炊いて、小分け冷凍すると忙しい時も便利ですよ」
- 「コンビニなら“もち麦入りおにぎり”が手軽です」
- 「白米を全部変える必要はありません。週に何回か取り入れるだけでも効果があります」
👉 “イメージで伝える”ことが指導のポイントです。
5. 栄養士のための炊き方ガイド
✅ もち麦ごはん(白米+もち麦30〜50%)
- 白米2合(300g)+もち麦0.6〜1合(90〜150g)
- 水は白米2合分+もち麦分の1.5倍
- 炊飯器の通常モードでOK
💡 白米の3〜5割を置き換えると、味もなじみやすく食物繊維がしっかり増える。
✅ 玄米ごはん(100%)
- 玄米2合(300g)+水(白米の約1.5倍)
- 炊飯器の「玄米モード」推奨(ない場合は浸水6〜8時間)
- 圧力鍋を使うとふっくら仕上がる
💡 プチプチ食感で噛みごたえがあり、満腹感もアップ。
6. ワンポイントアドバイス
- もち麦=混ぜるだけで導入しやすい
- 玄米=硬さがあるため、まずは週1回・少量から始めるのがおすすめ
👉 指導の際は「全部を変える必要はない」「できるところから始める」で患者さんのハードルを下げましょう。
まとめ
主食の工夫は、血糖管理に直結するシンプルで効果的なアプローチです。
- 食物繊維を増やすことで血糖の上がり方をゆるやかに
- 満腹感や腸内環境改善にもメリットあり
- 少しの工夫(麦を混ぜる・玄米を週に取り入れる)から始められる
👉 栄養指導では「続けられる工夫」を提案し、患者さんが“日常に取り入れやすい形”を一緒に見つけていきましょう。

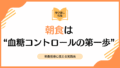

コメント