導入文
高血圧や糖尿病など生活習慣病の予防・治療において、「減塩」は最も基本的かつ重要な栄養指導の一つです。とくに管理栄養士が病院や特定保健指導の現場で患者さんに説明する際には、最新のガイドラインを整理して理解しておくことが欠かせません。
2025年版「日本人の食事摂取基準」では、食塩相当量の目標値が示されました。また、日本高血圧学会やWHO(世界保健機関)でも、より厳しい減塩目標が推奨されています。本記事では、これら最新情報を整理し、「糖尿病 食事指導」を実践する管理栄養士向けに、現場で活用できる減塩指導のポイントをまとめます。
1. 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」における減塩目標
厚生労働省が公表した「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、生活習慣病予防の観点から以下の目標値が設定されています。
- 男性:7.5g未満/日
- 女性:6.5g未満/日
さらに、高血圧や慢性腎臓病(CKD)予防を目的とした場合には、成人男女ともに「6.0g未満」と、より厳しい目標値が提示されています。
注目すべきは、「2020年版と同じ値を維持した」という点です。すでに国民の食塩摂取量は徐々に減少傾向にある一方で、依然として平均摂取量は9〜10g程度と高い水準にあり、さらなる減塩の実現が課題とされています。
栄養指導の現場では、患者さんに対し「1日あたり約2g減らすと、血圧が下がる可能性がある」という具体的な説明を行うと理解が得られやすくなります。また、糖尿病患者においても高血圧合併例は多いため、「糖尿病 食事指導」において減塩の説明は必須です。
2. 日本高血圧学会の減塩推奨
日本高血圧学会は、2021年改訂の「高血圧治療ガイドライン」において、一般成人を対象に「1日6g未満」を推奨しています。これは、国内外の大規模研究で減塩による降圧効果や心血管疾患予防効果が明らかになっているためです。
特に高血圧患者や糖尿病合併例では、食塩摂取量を6g未満に抑えることで血圧コントロールが改善し、降圧薬の使用量を減らせる可能性が報告されています。
臨床現場では、栄養士向けの食事指導において「味噌汁の汁を減らす」「漬物の量を減らす」「加工食品の選択に注意する」といった具体例を挙げることが有効です。また、患者さんに実際の食事記録を確認してもらい、食塩相当量の「見える化」を進めることも重要です。
3. WHO(世界保健機関)の国際的基準
WHOは成人に対して「1日5g未満(ナトリウム換算2,000mg未満)」を強く推奨しています。これは国際的に最も厳しい基準であり、心血管疾患予防効果が強く示されています。
WHOの基準は国際的な健康政策の指針として用いられており、各国の減塩戦略に影響を与えています。日本においても、将来的には「5g未満」を視野に入れた政策的取り組みが進められる可能性があります。
臨床現場の栄養士にとっては、「現実的な達成目標」と「理想的な国際基準」との間で、患者さんに合わせた減塩指導を行うことが求められます。特に糖尿病患者では、腎症や心血管疾患リスクを考慮し、可能であればWHO基準に近づける指導が望ましいでしょう。
4. 現場で使える減塩指導の実践ポイント
食品選びの工夫 ハム・ソーセージ・漬物・カップ麺などの加工食品は食塩量が多い食品です。 → 「毎日」ではなく「週数回まで」「量を半分に」など、頻度や量を減らす工夫を促しましょう。
調理の工夫 レモンや酢などの酸味、スパイスやハーブの香りを活かすことで、塩分を減らしても満足感を保てる味付けが可能です。 → 例:唐揚げにレモンを添える、サラダにこしょうやバジルを使う。
外食・コンビニ対応 1日6g以下を目指す場合は、1食2g〜2.5gが目安。 → 丼や麺類では汁を残す、タレやドレッシングは半量に。 → コンビニでは「おにぎり+サラダ+減塩惣菜」の組み合わせを提案。
患者との共有方法 「1食2〜2.5g」「1日6g未満」といったシンプルな数値で伝えると理解しやすいです。 → 図や表、食品写真を使って説明すると実感が湧きやすくなります。
行動変容を支える声かけ 「無理のない範囲でできることから」「昨日より少し薄味を」など、小さな成功体験を積み重ねる声かけが効果的です。
まとめ
2025年版の最新ガイドラインを整理すると以下のようになります。
✅ 日本人の減塩目標
男性:7.5g未満/日
女性:6.5g未満/日
✅ 高血圧・CKD予防では
成人男女とも:6.0g未満
✅ 日本高血圧学会
「1日6g未満」を強く推奨
✅ WHO
「1日5g未満」を国際的な基準として推奨
管理栄養士が病院や保健指導で栄養相談を行う際には、これらの基準を理解したうえで、患者の背景や行動変容ステージに応じた減塩指導を行うことが大切です。「糖尿病 食事指導」を行う際にも減塩の重要性を取り入れ、日常生活で実践できる具体的な工夫を伝えることが、長期的な疾患予防と健康寿命の延伸につながります。
参考文献
- 厚生労働省. 『日本人の食事摂取基準(2025年版)』最終報告書. 2024年. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00123.html
- 日本高血圧学会. 『高血圧治療ガイドライン2021』. 2021年. https://www.jpnsh.org/
- WHO. “Guideline: Sodium intake for adults and children.” 2012. https://www.who.int/publications/i/item/9789241504836
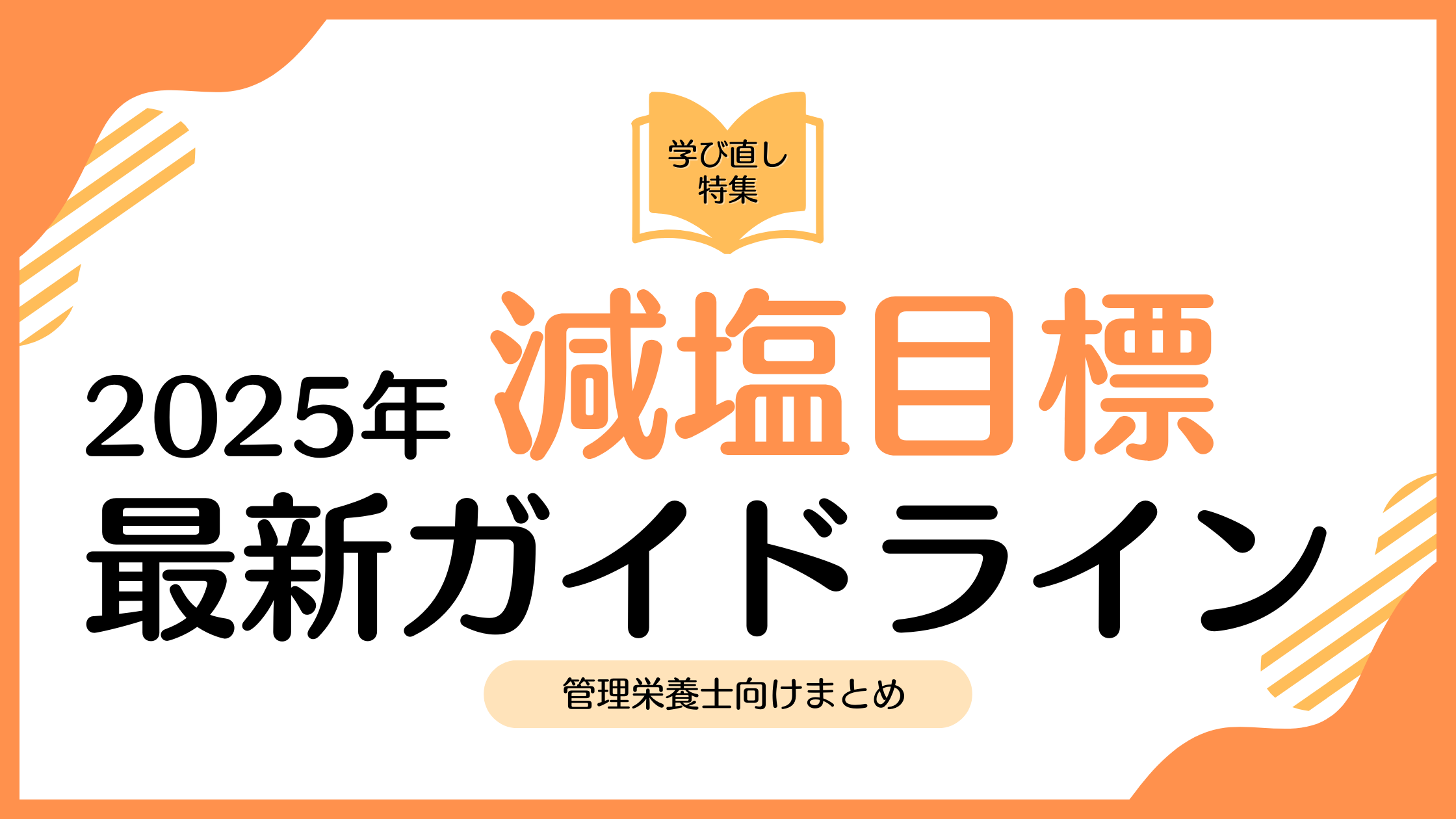


コメント